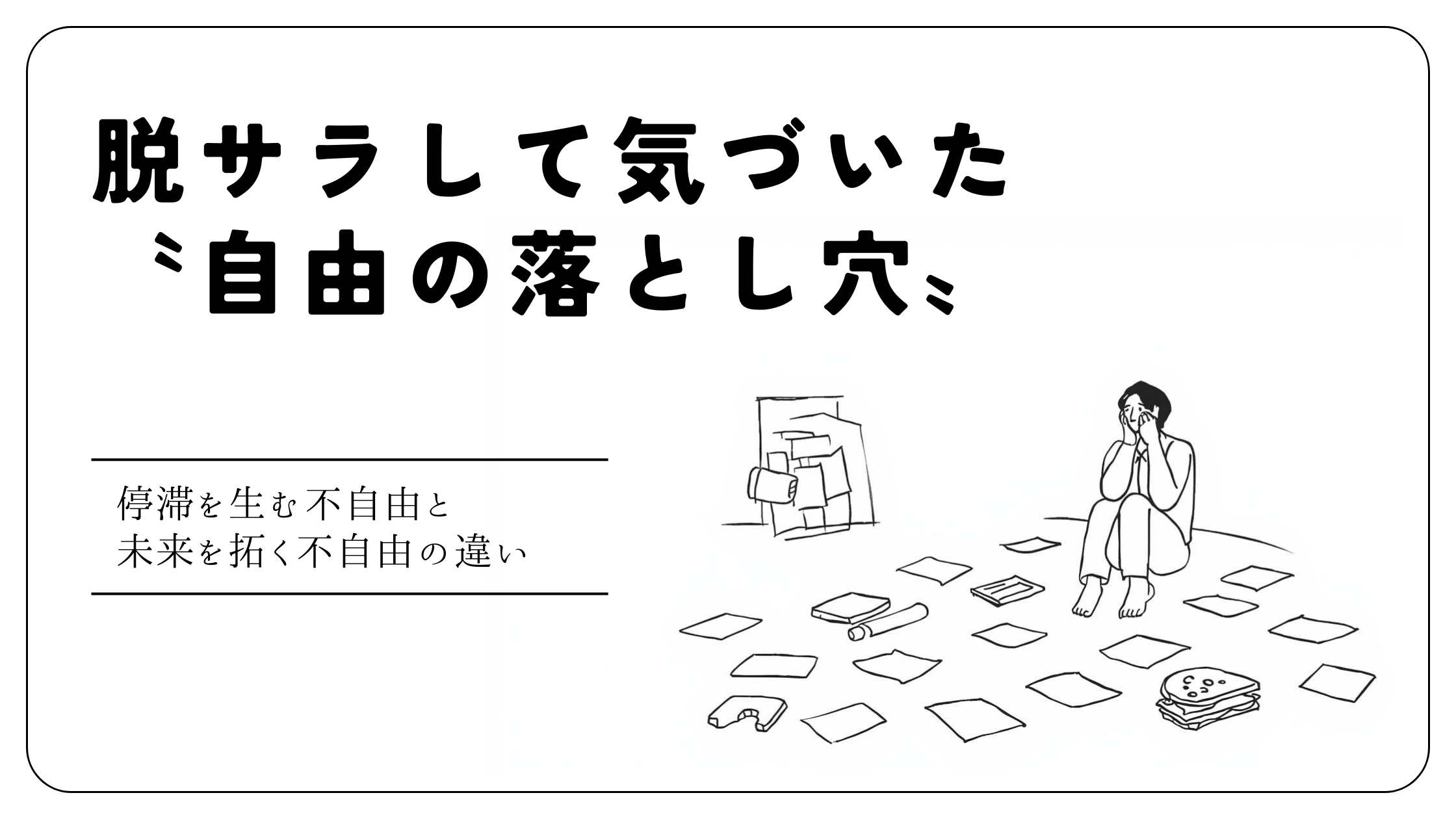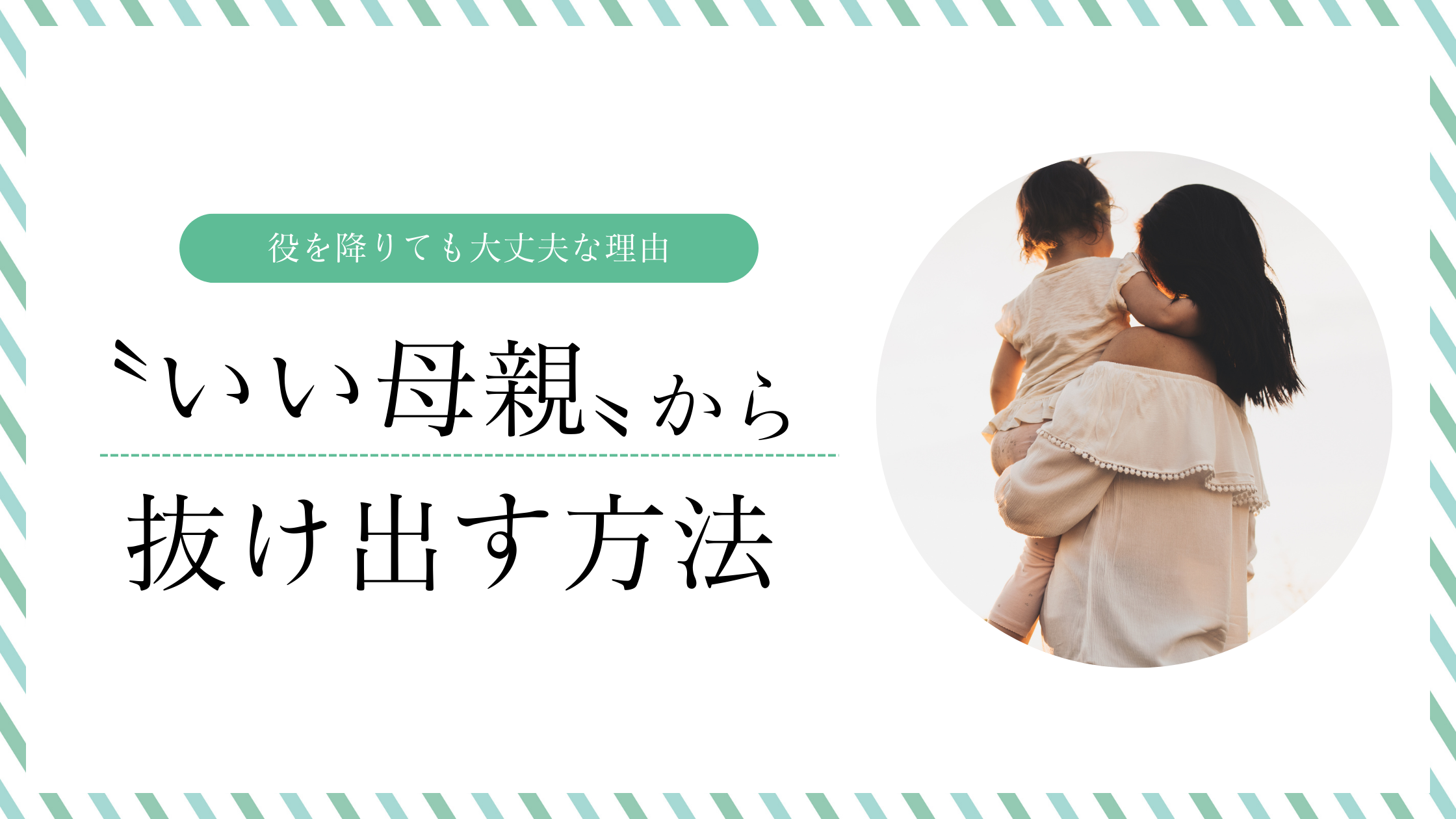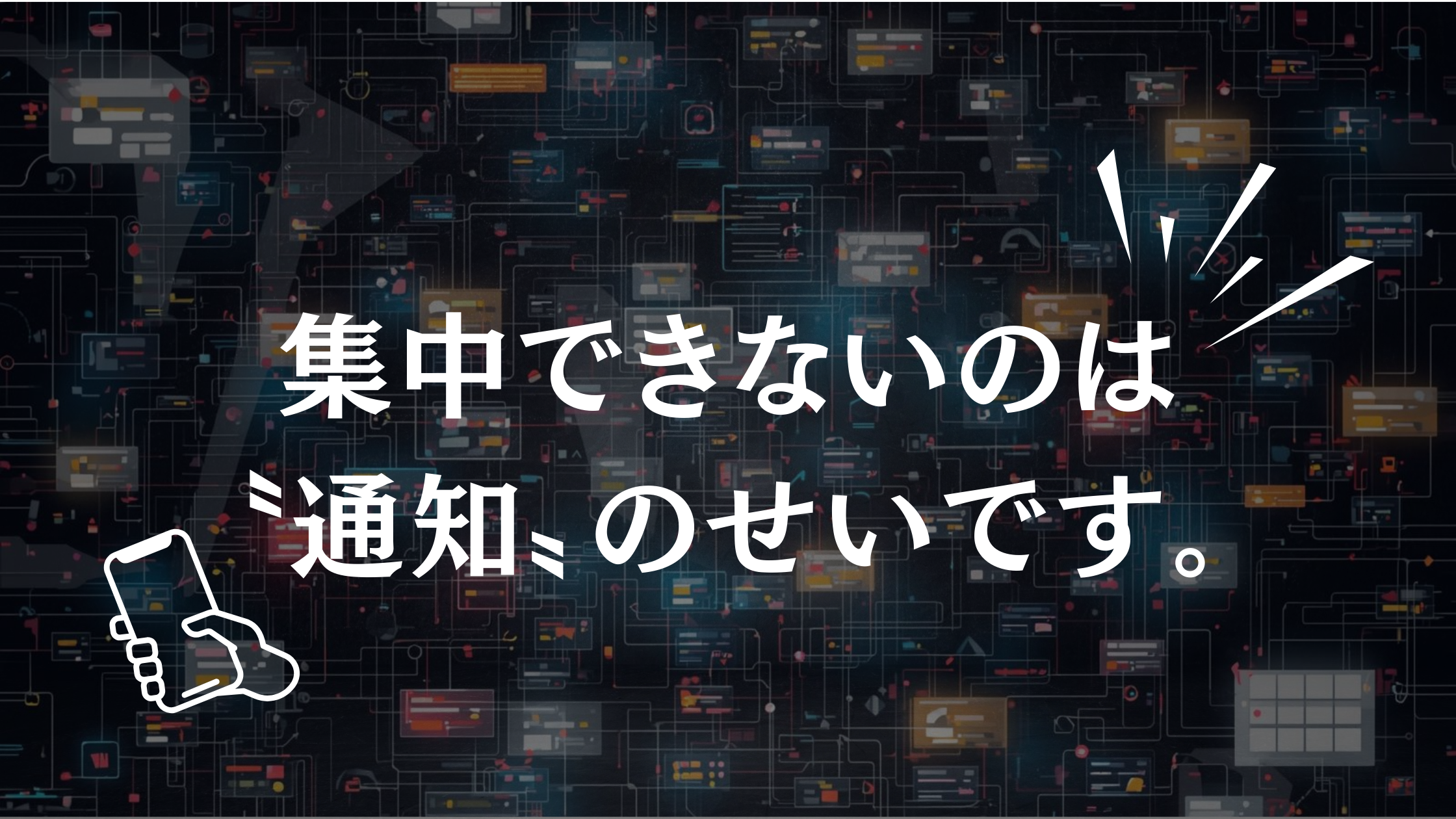不安は脳のバグ?乗り越える力に変える3つの視点
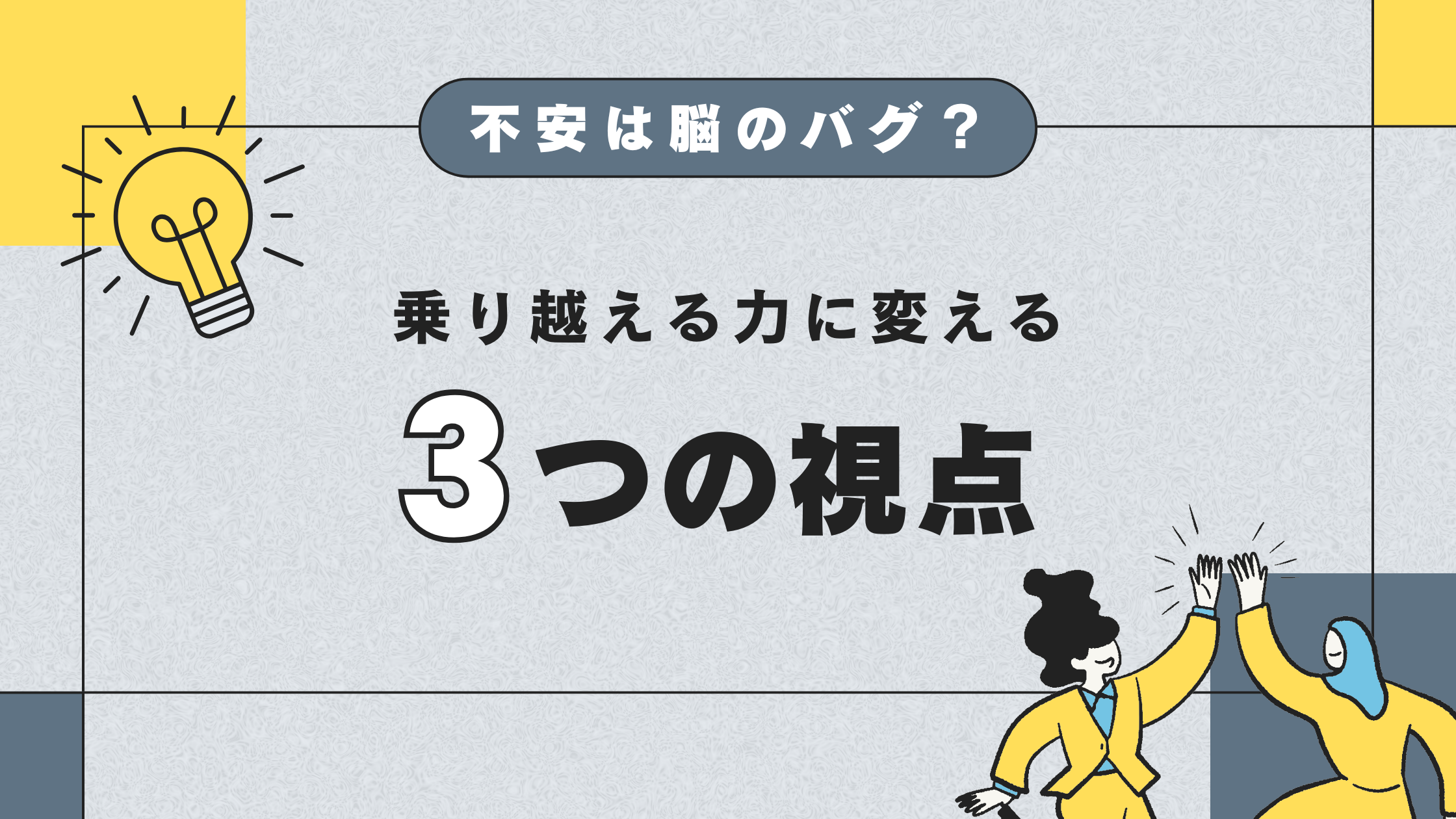
こんにちは、りさです!
さてさて、ぬるま湯脱出プログラムが始動してから3週間。
みなさまいかがお過ごしでしょうか・・・!
きっと
「よし!やったる!!!」っていう日もあれば
「全然ダメじゃん・・・」って
急に不安が襲ってきたり。
そんな風に、私たちは日々の中で
どうしても〝不安〟と隣り合わせで生きています。
時間がないように感じるのも、
集中できないのも、
実はその裏に不安や孤独、責任感といった感情が
隠れていることが多いのです。
あなたも心当たりはありませんか??
やらなきゃいけないのに、ついスマホに逃げたり。
大事な作業よりも、片づけや細かい用事を優先してしまったり。
気づけば、本当に大切な時間がどんどん削られていく。
では、不安とどう向き合えば、
振り回されずに前へ進めるのでしょうか。
結論から言えば
「不安を消そうとしない」ことです。
考えまいとするほど、
脳はその事でいっぱいになります。
大事な試験やプレゼンの前夜、
「失敗したらどうしよう」と浮かぶたびに、
「大丈夫、大丈夫」と頭を振る。
でもなぜか、その場面ばかりが鮮明になっていく。
むしろ「失敗する瞬間」の映像を
自分で監督しているかのように、
細部までリアルに再生されてしまう。
胸のあたりが重くなり、呼吸が浅くなる。
眠ろうとしても寝返りばかり増えて、
天井の模様を眺め続けてしまう。
「考えちゃダメだ」と思えば思うほど、
その言葉がトリガーになって
頭の中に同じ映像が流れ込んでくるのです。
私もよく最悪のパターン上映会を
勝手に開催してしまうタイプでした。。
人前で話す前には、
噛んでしまう自分
頭が真っ白になる自分
会場がシーンと静まり返る場面・・・
そんな映像が延々と再生され、体も硬直していく。
でもここで大切なのは、
無理やりポジティブに塗り替えることではありません。
「大丈夫、大丈夫」と笑顔をつくっても、
一瞬は安心できても心のどこかに違和感が残る。
表面では元気そうに振る舞っていても、
内側では〝見てはいけない不安〟が暴れているのです。
だからこそ必要なのは、
「不安を感じている自分がいる」
という事実を受け入れること。
「私は今、不安なんだ」とそのまま認める。
すると、不安は無理に押し込めた時よりも
少しずつ静まっていくのです。
そのうえで最初の一歩は、
「変えられるもの」と「変えられないもの」を分けること。
たとえば、
細部に厳しい上司の性格を
今すぐ変えることは難しい。
でも、自分の姿勢は変えられます。
提出前のチェックを変えてみたり、
指摘を「粗探し」ではなく
「見落としに気づかせてくれる助け」と再定義する。
子どもが朝起きられないなら、
叱るより生活リズムや就寝前の環境を工夫する。
リビングの照明を少し暗めにする。
寝る前のテレビやスマホをやめて読書に切り替える。
朝にお気に入りの音楽を流す。
小さな工夫が結果を変えることは多いのです。
これは、ブログ運営でも同じ。
検索順位の変動は、自分がコントロールできない領域です。
アルゴリズムの影響で一夜にして順位が下がることもある。
それに執着して不安を募らせても結果は動きません。
けれど、
記事の質や内部リンクの工夫や
読者の滞在時間を意識した文章改善は、
すぐに自分の手で取り組めること。
外的要因ではなく、
内的要因にエネルギーを注ぐことで、
不安がやわらぎます。
そして次に大切なのは、
「自分の人生に主体的に参加する」こと。
幸福度を押し上げるのは、
肩書きや収入、見た目の派手さではなく、
日常のささやかな行動です。
たとえば、
道端で落とし物を拾って渡した瞬間や、
エレベーターで「開く」ボタンを押して待ってあげた時の
小さなありがとう。
それだけで気分が変わることはないでしょうか。
こうした小さな行動が、
自分の存在価値を思い出させてくれるというか。
スマホを伏せて目の前の人に集中するのでもいいし、
10分だけ散歩するのでもいい。
そんな習慣のほうが、
SNSで「いいね」を100もらうよりも
幸福度を高めてくれると思います。
外から与えられる評価ではなく、
内側からじんわり湧いてくる充実感。
それを選び取れるかどうかが、
不安との距離感を決めますよ!
もうひとつ大切なのが「負荷の価値」です。
私たちは「できるだけラクに」「効率的に」
を求めがちです。
でも、道のりが平坦すぎると、
達成したときの喜びは
どこか薄くなってしまうもの。
筋トレをすると筋繊維はいったん壊れ、
修復の過程でより強くなる。
これが超回復ですね!
人生も同じで、
ある程度の負荷をくぐり抜けるからこそ、
その先の幸福感は何倍にも大きく膨らみます。
私自身、1年間ほとんど成果が出なかった時期がありました。
正直、毎日が重くて、
辞めたくなる気持ちと何度も戦いました。
けれど、その時間を経たからこそ、
成果が出たときに「自分は本当にやり抜いた」
と心から思えたのです。
もし1ヶ月で偶然結果が出ていたら、
「これはたまたま?」
と疑って不安が残ったでしょうし、
喜びもここまで大きくはなかったはずです。
つまり負荷は、人生に必要なプロセス。
避け続ければ一時的にラクはできますが、
逆に成長のチャンスを奪ってしまうのです。
そしてこの「負荷」で大事なのは、
「乗り越えた過程」こそが
人を感化するということ。
華やかな結果よりも、
苦戦しながらも一歩ずつ進んだ物語に、
人は心を動かされます。
私の発信に共感していただけるのも、
失敗や停滞の時期をどう過ごしたかを
率直に語っているからだと感じます。
人が惹かれるのは〝完成された過去〟ではなく、
〝挑戦し続けている今〟。
そこにこそリアルさがあり、
共鳴が生まれていくのです。
とはいえ、
「それでも不安だよ。。」
という方もいるかもしれません。
人は「0か100か」の思考に陥りがちです。
ひとつ失敗しただけで
「私は何をやってもダメだ」
と全体を決めつけてしまう。
でも実際には、得意なことも成功したことも必ずあるのです。
私自身も、学生時代は
「人前で話すのは向いていない」と思い込み、
緊張で声が震えるたびに自信を失っていました。
けれど、その思い込みがほどけた今では、
毎朝こうして人前で話すことが
当たり前になっています。
思考が変われば、行動も変わるのです。
そして、不安から逃れるために
人が取りがちなものが回避行動です。
やるべきことがあるのに、掃除を始めてしまう。
勉強の代わりにゲームを起動してしまう。
あるいは「体調が悪いから」
と理由をつけて先送りしてしまう。
短期的には安心感がありますが、
長期的には虚無感や後悔につながります。
起業したいと考えながら、
情報収集ばかりして行動に移せないのも
同じパターンです。
何度も言いますが、完璧を目指す必要はありません。
小さくてもいいから、一歩動くこと。
その一歩が不安をやわらげ、
未来を少しずつ変えていきます。
そもそも、不安の大半は現実になりません。
「九割以上は起きない」とも言われています。
これは人間の脳が、
狩猟採集時代から続く
〝危険を過敏に察知する仕組み〟
を持っているから。
当時は命を守るために必要でしたが、
現代では誇張された不安として働くことが多いのです。
たとえば、上司から
「ちょっと話あるから」と言われた瞬間。
それだけで頭の中では
「何かやらかした?評価が下がった?クビになる?」
と最悪のシナリオを勝手に展開してしまう。
心臓がバクバクして、仕事どころじゃなくなる。
でも実際に話してみると
「次の案件どう進めようか」とか
「最近どう?」といった
雑談程度で終わることがほとんどです。
不安が湧くのは、いわば脳のバグのようなもの。
その仕組みを知っておくだけでも、
「あ、今また脳の癖が出たな」と客観視でき、
不安に飲み込まれにくくなるのです。
最後に大切なのは
「私はどう生きたいか」
と自分に問いかけること。
誰かの期待や常識に合わせるのではなく、
自分の本心を少しずつ言葉にしていく。
それだけで、不安の波に揺さぶられにくくなります。
怖さは消えなくても大丈夫です。
不安を完全になくそうとするのではなく、
「振り回されない自分」を作っていきましょう。
大切なのは、不安を理由に立ち止まらないこと。
「それでも一歩」を積み重ねた人にしか見えない景色が、
必ず先に待っています。
私たちは何度でも、新しいスタートを切ることができるのです。