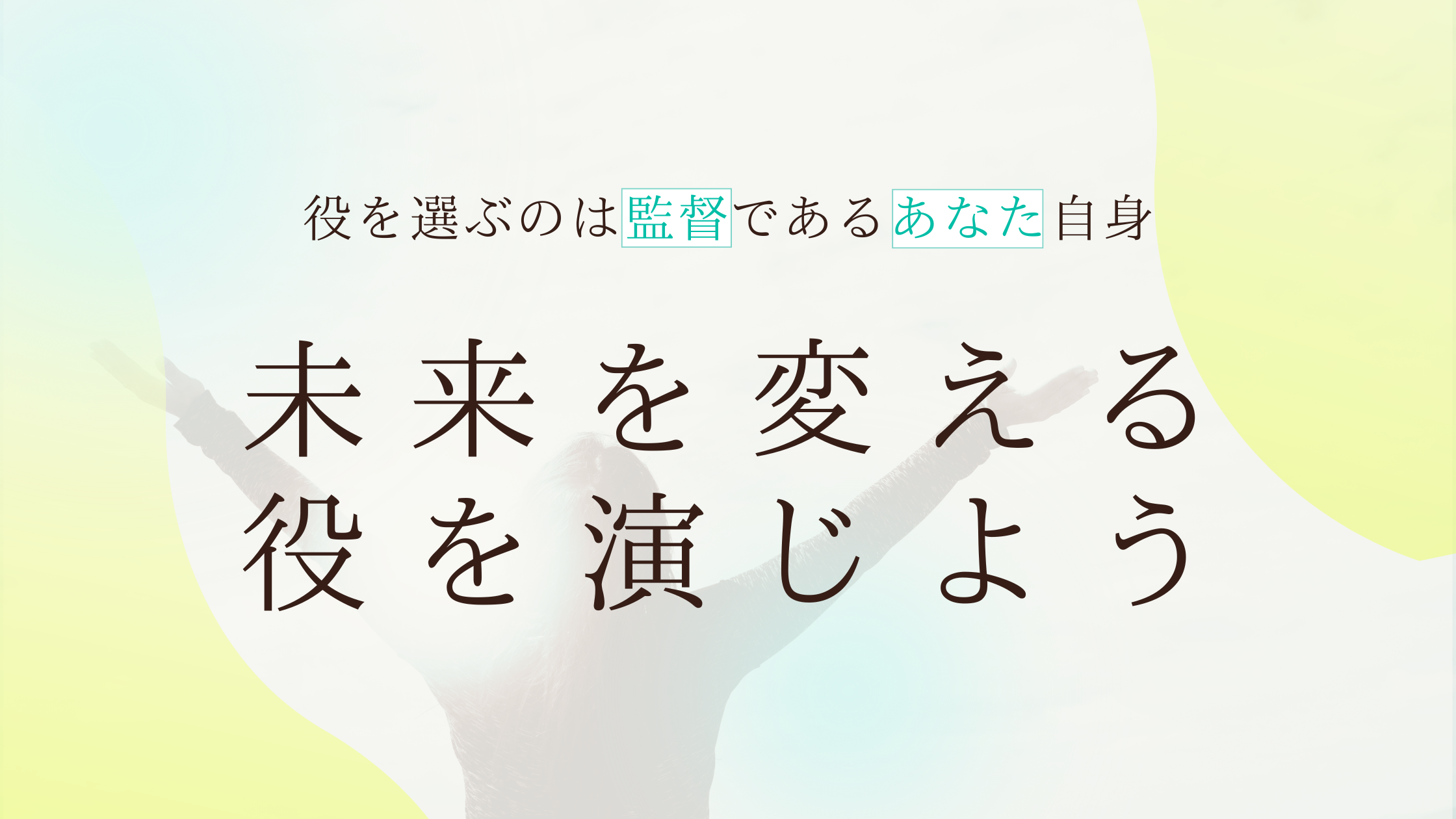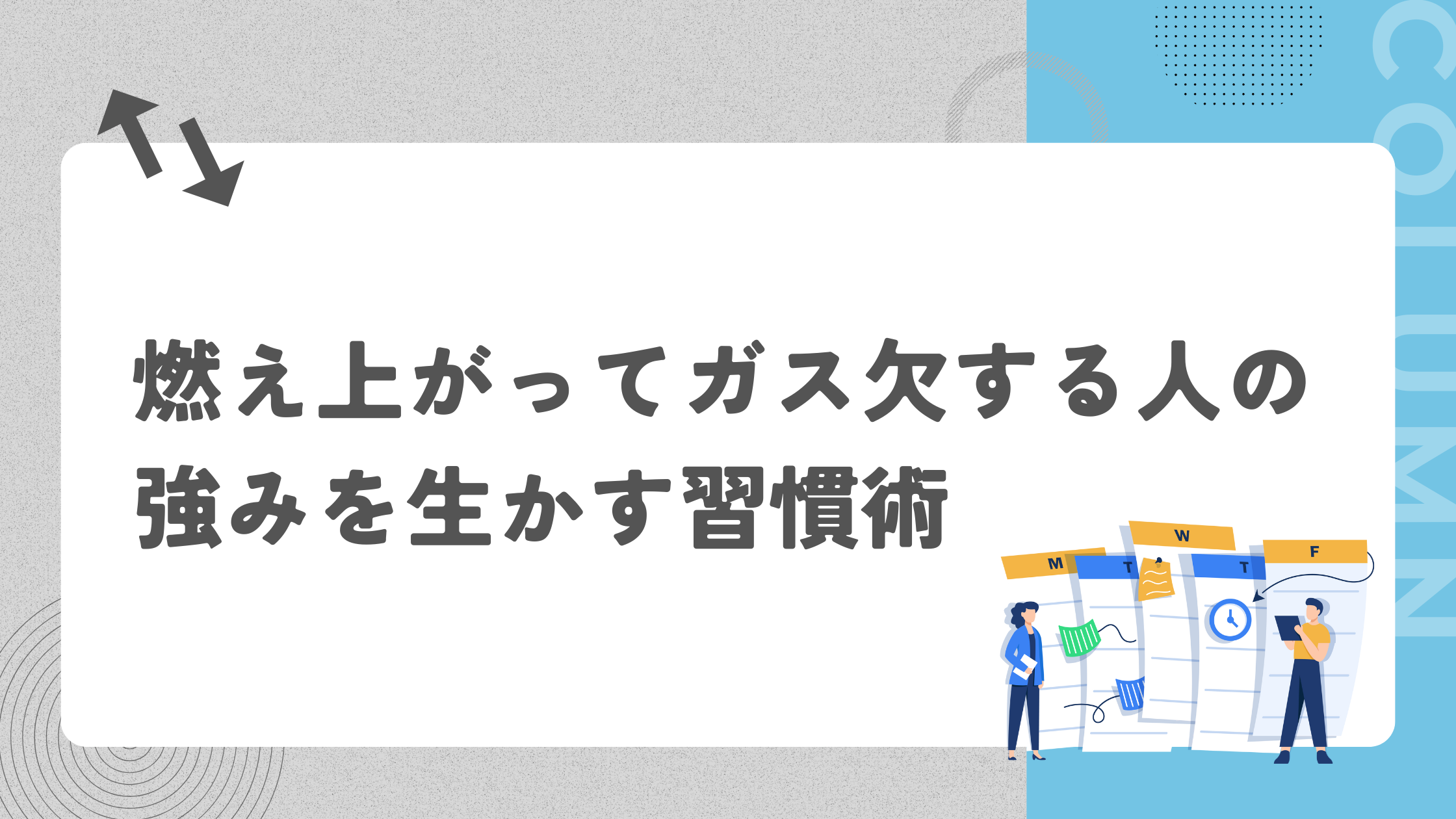「ほんとうの幸い」を探し続けるために

こんにちは、りさです!
さて、今日お話ししたいのは
「自己犠牲や本当の幸せ」
についてです。
このテーマを考えるとき、
どうしても思い出す作品があります。
それが、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』。

学生時代に出会って強烈に印象に残った作品で、
最初は活字ではなくアニメで観ました。
アニメ映画だと、猫になっています。
主人公のジョバンニと友人のカムパネルラが
銀河鉄道に乗って星空を旅する物語。
暗くて幻想的で、儚くも美しい世界観でした。
お話を知らない人のために、
あらすじを説明しますね。
主人公のジョバンニは、
貧しい家に生まれ、
父は不在、母は病気で寝込んでいます。
そのため、まだ子どもでありながら
働かざるを得ない境遇にあります。
昼は学校へ行き、帰ってからは活版所でアルバイトをし、
夜には病床の母の看病をする。
心の支えがなく、孤独を抱えながら
毎日を必死に生きていました。
しかし、そんな苦労を理解してくれる友達は
周りにいません。
むしろ、クラスメイトたちは
「父親がいないこと」をからかうのです。
一方で、同級生のカムパネルラは
裕福な家庭に育ち、皆に慕われる人気者。
二人は昔は仲が良かったし、
カムパネルラ自身は決して
ジョバンニを嫌っているわけではないのに、
クラスの人間関係のなかで
自然と距離が生まれてしまいます。
そして、お祭りの夜。
孤独を抱えたジョバンニが
一人で丘を駆け上がると、
突然現れたのが銀河鉄道。
そこで偶然にもカムパネルラと再会し、
二人は一緒に、星空の旅へと出発します。
この映画を見た当時の私(中学生)は、
「自己犠牲って、切ないけど尊い…」
と単純に受け取りました。
その印象はずっと心に残っていて、
「いつかちゃんと誰かと共有したいな」
と思っていたんです。
そこで今回、
「これはぬるま湯のテーマにもつながる!」と感じて、
あらためて原作を最初から丁寧に読み直してみました。
すると、
学生時代に受け取った印象とは
まるで違う感覚が心に残ったんです・・・!
当時は
「自己犠牲って尊い」
「カムパネルラってなんていい子なの」
という表面的な感動で終わっていたのですが、
大人になった今読むと、
登場人物一人ひとりの背後にある孤独や葛藤、
そして残された人の悲しみまで
強く感じるようになりました。
あの頃は気づけなかった〝割り切れなさ〟や〝矛盾〟が、
人生経験を積んだ今だからこそ鮮明に見えてくるんです。
さて、ここで大きなネタバレですが、(先に原作を読みたい方はここで止めてね)
銀河鉄道は「死者を運ぶ列車」。
ジョバンニだけが生きていて、
車両にいる他の乗客はみな亡くなった人たち。
旅の途中で出会う人々は
それぞれ「死の直前に抱いた想い」や「後悔」「祈り」を語り、
ジョバンニに問いを投げかけていきます。
例えば、蠍。
小さな虫を食べて生きてきたけれど、
イタチに追われて井戸に落ちたとき、
初めて
「どうせ死ぬなら自分を役立てればよかった」
と悔やみます。
そして最後に、星(アンタレス)となって光り輝く。
私たちも日常の中で「いつかやろう」
と思いながら後回しにしてしまうことありません??
「ありがとう」の一言を伝えること。
気になっていた友人に連絡すること。
ほんの数分でできるのに、つい明日に延ばしてしまう。
でも、明日が必ず来るとは限らないんですよね。
だから思いついたときにちゃんと行動すること。
それが、後悔のない生き方に繋がると思います。
そして、物語の途中には、
タイタニック号の沈没を思わせるシーンも描かれています。
船が沈没して亡くなった人々が
銀河鉄道に乗り込んでくるのですが、
その中に家庭教師の青年と、
彼が預かっていた二人の子どもたちがいました。
青年は自分の責任として
「せめてこの子たちだけは助けたい」
と必死になります。
しかし、救命ボートの周りには
他にも助けを待つ子どもたちが大勢いて、
「この二人だけを優先していいのか」
と激しく葛藤するのです。
結果的に預かっていた子どもたちを救うことはできず、
三人一緒に海に沈んでしまい、
その魂が銀河鉄道に乗ってきた……という流れです。
家庭教師の青年は、決して怠けていたわけでも、
理想を追いすぎていたわけでもない。
彼は「二人の命を守るべき」
という強い責任感と、
「他の子どもたちを犠牲にしてまで守ってよいのか」
という罪悪感の間で、
最後まで判断を下せなかった。
結果として、彼が預かっていた二人の子どもも、
自分自身も助からなかったことへの無念が、
青年を苦しめたのだと思います。
これって私たちの生活でもありますよね。
(まあここまで重くはないかもですが)
たとえば
「家族と仕事、どちらを優先すべきか」
「目の前の一人を助けるのか、それとも全体を見て判断するのか」。
どちらも大切だからこそ、選ぶのが難しい。
結局、動けずに時間だけが過ぎていく。
そして、後になって
「あのときどうして決められなかったんだろう」
と自分を責めたり、
取り返せない後悔を抱えたりする。
家庭教師の青年は
「正しい選択」をしようとして立ち尽くし、
最後まで決断できなかった。
でもそれは弱さではなく、
「何が本当に正しいのか分からない」
人間の普遍的な苦悩なのだと思います。
つまり私たちは、
完璧な答えを出そうとするよりも、
たとえ不完全でも「その瞬間に選び、動く」ことを
大事にしなければならないのかもしれません。
そして、カムパネルラの死。
祭りの夜、ザネリという友達が川に落ちてしまい、
カムパネルラは迷うことなく飛び込みました。
結果としてザネリの命は助かりましたが、
カムパネルラ自身は戻ってくることはありませんでした。
学生時代の私は、この場面をただ
「カムパネルラはなんて良いやつなんだ」
と純粋に受け止めていました。
自分を犠牲にしてまで他人を救う。
その行為そのものが美しく、心を震わせたのです。
けれど、今改めて読むと違う感覚があります。
自己犠牲は確かに尊い。
しかしその裏側で、
残された者たちは深い悲しみを背負うことになる。
カムパネルラの父親は川辺で息子を探し続けました。
犠牲によって救われる命がある一方で、
同時に失われる命もある。
その矛盾は、決して簡単に割り切れるものではありません。
むしろ、その「割り切れなさ」こそが現実であり、
人間が背負う宿命のようにも思えるんです。
私たちは日常の中でも、
小さな「誰かのための自己犠牲」を繰り返しています。
家族のために自分の時間を削る。
職場で仲間のために自分の役割を後回しにする。
もちろん、それ自体は尊い行為です。
けれど、そこには美しいだけではなく
「自分は報われなかった」
「なぜ自分ばかり」
という感情も同時に生まれる可能性がある。
つまり、自己犠牲をそのまま美化するのではなく、
どうすれば自分も相手も幸せになれるのか
を考えることが大切なのだと思います。
ジョバンニはこう言います。
「カムパネルラ、また僕たち二人ふたりきりになったねえ、どこまでもどこまでもいっしょに行こう。僕はもう、あのさそりのように、ほんとうにみんなの幸のためならば僕のからだなんか百ぺん灼いてもかまわない」
それにカムパネルラも応じます。
「うん。僕だってそうだ」
けれど、その後すぐにジョバンニはこうも言っています。
「けれどもほんとうのさいわいはいったいなんだろう」
その問いに、カムパネルラも
「僕わからない」
と答えるしかありませんでした。
実際に、カムパネルラが自身の行動に対し
苦悩しているシーンがあります。
「おっかさんは、ぼくをゆるしてくださるだろうか」
「ぼくはおっかさんが、ほんとうに幸になるなら、どんなことでもする。けれども、いったいどんなことが、おっかさんのいちばんの幸なんだろう」
「ほんとうの幸い」とは何か。
明確な答えは示されていません。
だからこそ、読むたびに解釈が変わるし、
読む人の生き方や価値観によって感じ方も違う。
まるで鏡のように、
自分自身の内面を映し出す作品なのだと思います。
これを日常に戻したときに大事なのは、
自分を削る自己犠牲ではなく、小さなギブ。
自己犠牲という言葉には
自分を削って差し出すようなイメージがあります。
けれどもギブは違います。
地中深くからこんこんと水が湧き出す泉のようなもの。
誰かのために無理やり搾り出すのではなく、
心の奥から自然にあふれて流れ出ていく。
続けても苦しくならないし、
流せば流すほどまた新しいエネルギーが湧いてくるんです。
ビジネスにおいても、同じことが言えます。
「どうすれば自分が売れるか」
「どうすれば数字を達成できるか」
だけを考えていると、長く続かず、
やがて息苦しくなります。
けれど「どうすれば相手が喜んでくれるか」
「この人の問題をどうすれば解決できるか」
という視点に立つと、
不思議とエネルギーが湧き出してくる。
お客様の笑顔や「助かったよ」という言葉が、
新しい力になって返ってきます。
これが自己犠牲ではなく、
ギブが生み出す循環なんです。
私自身、ブログや発信を続けてきて思うのは
「誰かに伝えたい」
「誰かの背中を押したい」
という気持ちがあるときほど頑張れるし、
夜中まで作業しても楽しいから続けられる。
逆に自分だけのための作業は、
すぐにしんどくなって続きませんでした。
ギブは、自分を削るものではなく、
むしろ自分の中の源泉を開いてくれるものなんですよ。
最後に。
『銀河鉄道の夜』が伝えてくれるのは、
「生きていなければ幸いを探し続けることはできない」
というメッセージです。
カムパネルラは自己犠牲のなかで命を落としました。
その姿は尊くもありますが、
彼がいなくなったあとに残されたのは、
父の深い悲しみや、友を失ったジョバンニの孤独でした。
犠牲の先には光と影の両方がある。
ジョバンニが背負ったのは
「死をもって示すこと」ではなく、
「生きて考え続ける責任」
だったのだと思います。
私たちも一緒。
人生の中で、辛さや苦しさに
押しつぶされそうになる瞬間があります。
「なぜ自分ばかり」と思うこともあるでしょう。
けれど、その体験さえも燃料に変えながら歩みを進めていけるのです。
悲しみを悲しみのままで終わらせない。
苦しみを苦しみのままで閉じ込めない。
そこから何かを学び取り、
自分も周りも幸せになる方向へと転換していく。
それこそが、生きている私たちに与えられた使命であり、
賢治が作品を通して問いかけた
「ほんとうの幸い」への道なのかもしれません。
だから、立ち止まってしまったときこそ思い出してほしいのです。
生きている限り、私たちは
「幸い」を探し続ける旅の途中にいる。
歩みを止めないかぎり、その答えに少しずつ近づいていけるのだと。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました!
※私もさらに理解を深め、また改めてこのテーマで
セミナーでも開きたいです・・・!(だいぶ不完全燃焼、、笑)
是非原作も読んでみてください↓