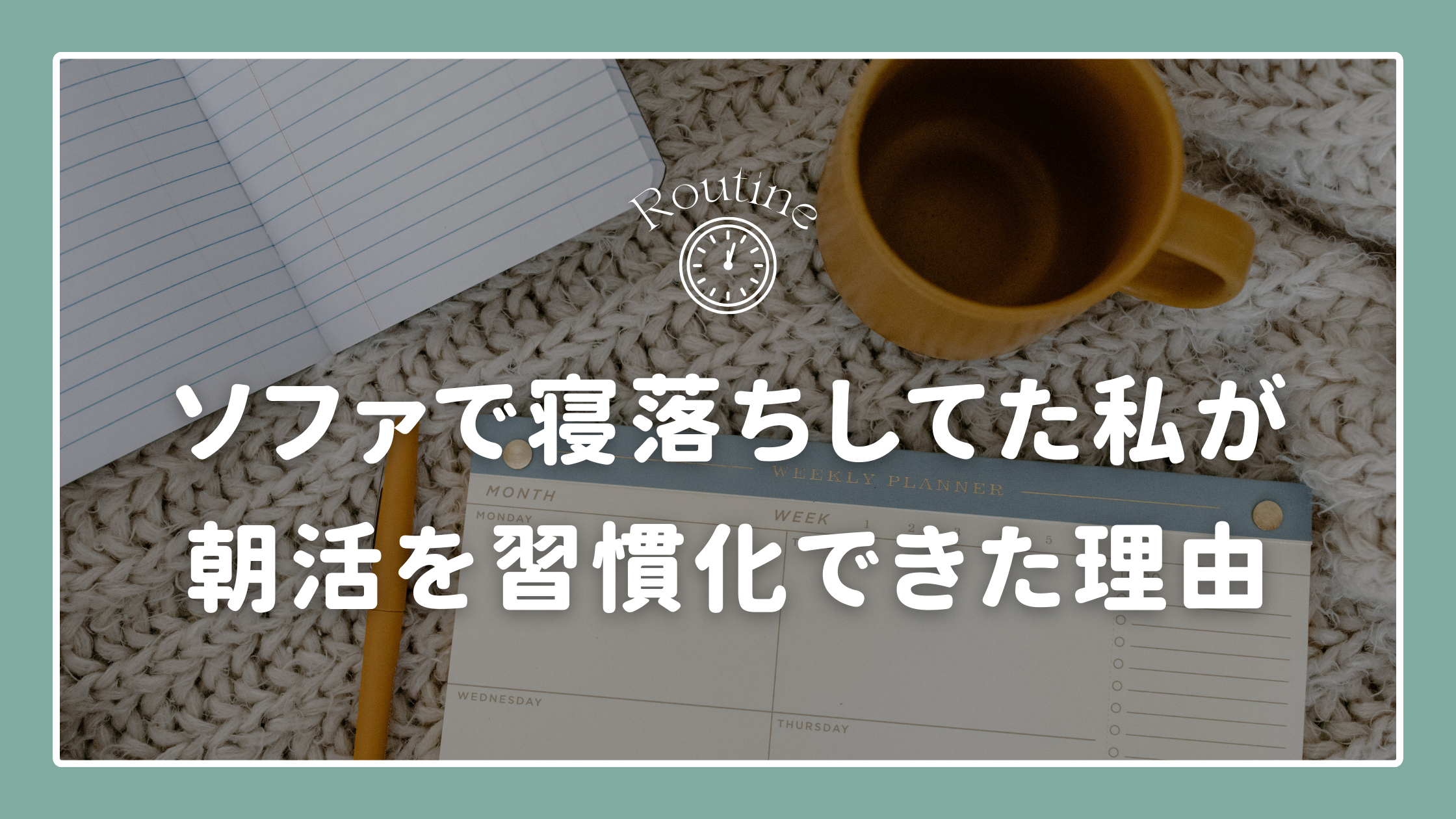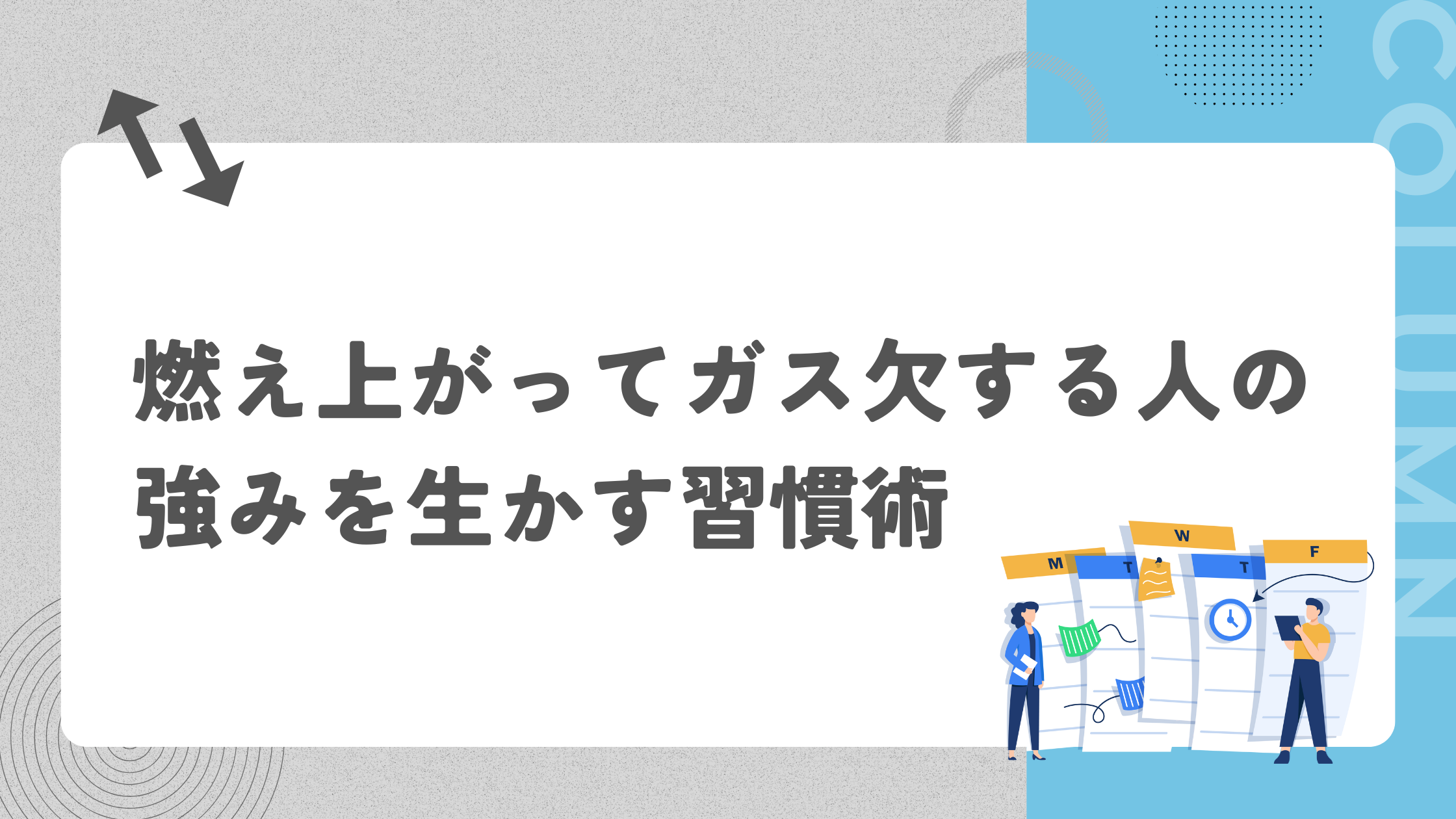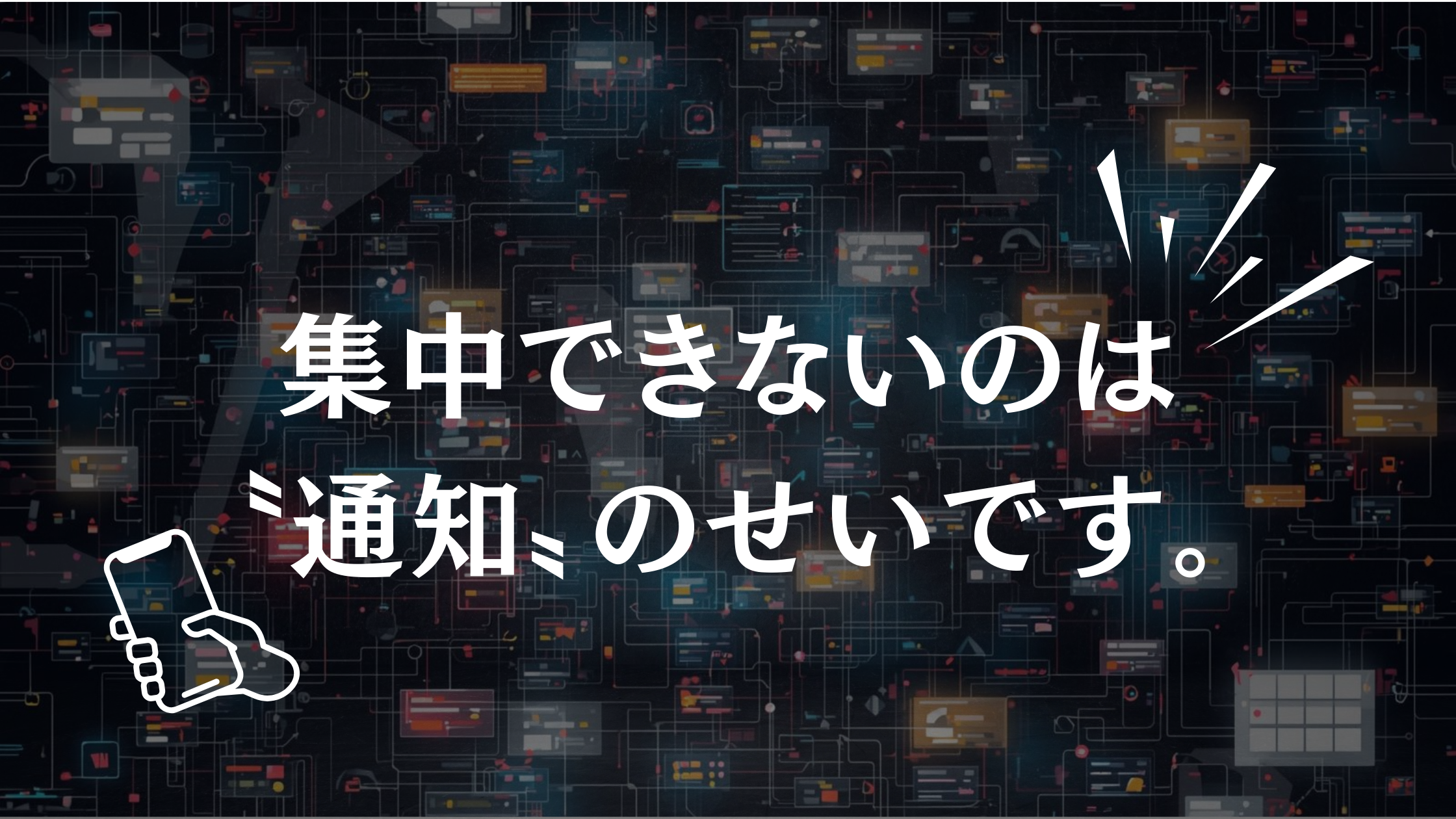〝燃えていない自分〟に気づいたときに最初にすべきこと
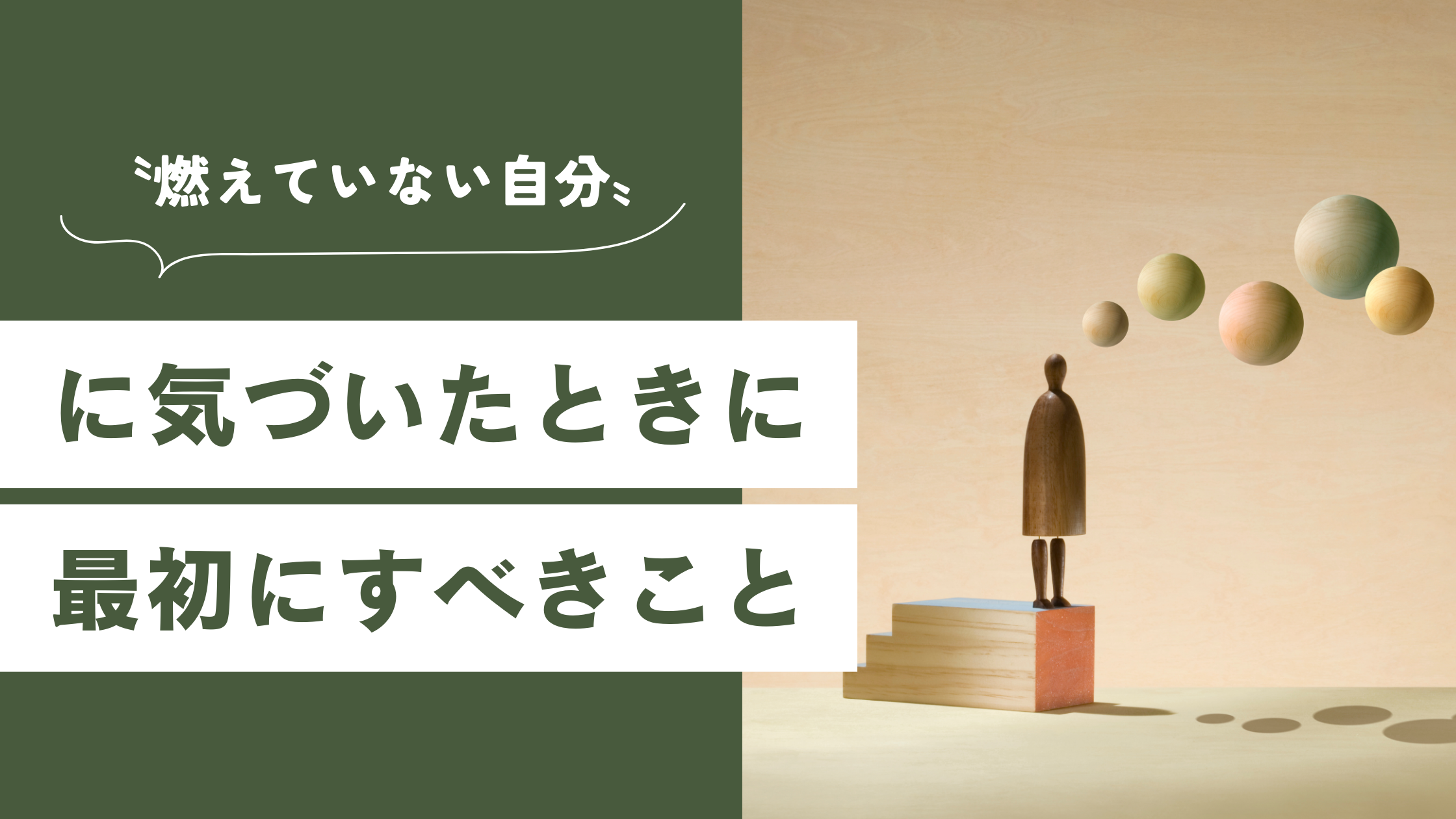
こんにちは、りさです!
今回は、
「燃えていない自分とどう向き合うか」
について話していきたいと思います。
先日、とある受講生さんのお話。
まぁ「しずかさん」という方なんですけども笑
彼女は以前から私のブログコンサルを受けていて、
今では自分でもコンサルタントとして活動しています。
そんな彼女が、今回の
「ぬるま湯脱出プログラム」を見たときに思ったのは、
「これはまさに自分のことだ」
という感覚でした。
「やりたい、挑戦したい」
その思いは確かにあったんです。
けれど同時に、猛烈に強いブレーキもかかりました。
「続かないかもしれない」
「必要だと分かっているけれど、直視すると怖い」
結果として、オープンチャットには参加したものの、
ライブを聞きに来たり、
アウトプットしたりは
「しない」
という選択をしたのです。
この話、きっと多くの人が心当たりがあると思います。
やればプラスになるのは分かっているのに、腰が重い。
頭の中では「やった方がいい」
と分かっているのに、実際に動けない。
行動すれば変わる未来が見えているのに、
なぜかそれを避けてしまう。
では、なぜ人は、そんな
「もったいない選択」をしてしまうのでしょうか。
理由はいくつかあります。
まずひとつは「失敗が怖い」という心理。
人は、行動そのものよりも
「行動した結果に対する評価」を恐れます。
たとえば新しい挑戦を始めても、
もし三日でやめてしまったら
「やっぱり続かない人だ」
と思われるのではないか。
自分自身も「またダメだった」
と感じてしまうのではないか。
そう考えると、挑戦する前から体が止まってしまう。
さらに厄介なのは、人は「失敗した未来」を
実際以上に大きく膨らませて想像してしまうことです。
挑戦したら、みんなに笑われるかもしれない。
信用を失うかもしれない。
評価が下がるかもしれない。
実際には、他人はそこまで自分を見ていないのに、
頭の中では〝世界中が自分をジャッジする〟
くらいの恐怖を抱いてしまうものです。
そしてこの恐怖、過去の経験とも結びついています。
学生時代に「三日坊主だね」と笑われた記憶。
職場で一度ミスをしたときに
「やっぱり頼りない」と言われた記憶。
そうした小さな出来事が積み重なって、
「失敗=自分の価値を下げるもの」
という思い込みを強化しています。
結果として、行動する前に
「どうせ続かない」
「また恥をかく」
と心の中で自分を裁いてしまう。
つまり、本当はまだ始めてもいないのに、
頭の中で〝未来の敗北シーン〟を上映し続けて、
自分を止めてしまうのです。
だからこそ必要なのは、
「失敗の意味づけ」を変えること。
三日で終わったなら、
それは「三日分は動いた」という証拠です。
ゼロよりも、三日の経験の方が確実に価値がある。
ゼロは何も残らないけれど、
三日やればそれは何か必ず残ります。
その小さな経験が次の挑戦の燃料になるんです。
そして、もうひとつは「比較」です。
人はどうしても他人と比べてしまう生き物。
これは本能的なものでもあります。
原始時代、人間は群れを作って生き延びてきました。
もし仲間より劣っていると見なされれば、
食料やパートナーを得られない、
場合によっては群れから排除される危険すらあった。
つまり「劣る=生存リスク」だったのです。
その名残で、現代の私たちの脳も
「比較」に敏感に反応します。
実際、脳は物理的な危険だけでなく、
社会的な危険も〝命に関わる〟こととして扱ってしまう。
だから他人の頑張りを見たときに
「自分は足りない」と感じると、
まるで命の危機にさらされているかのように
不安やストレスを覚えるのです。
例えば、同じ環境にいる仲間が
一生懸命頑張っている姿を見たとき、
「自分は足りない」
「ここまで熱くなれていない」
と感じてしまう。
他人の熱量を目の前にすると、
自分の火の弱さが突きつけられて、
途端に息苦しくなるのです。
SNSで毎日投稿している人を見たときに
「あの人はすごい。私は三日坊主で終わってしまった」と凹んだり、
勉強会やコミュニティで、
誰かが積極的に発言しているのを見たときに
「私は人前で話すのが苦手だ。やっぱり自分はダメだ」と落ち込んだり。
こうして比較の目で見れば見るほど、
自分の欠けている部分ばかりが浮かび上がり、
自信を削られていく。
すると人は、防衛本能として
「見ないふり」をし始めます。
自分より熱量の高い人を避ける。
「私は別にそこまでやらなくてもいい」
と言い訳をつくって距離を取る。
けれど裏返して考えると、
本当は気になっているから目をそらすということでもあります。
気になって仕方がないことは、実はできること。
人は本当に不可能だと思っていることには、
そもそも憧れすら抱きません。
例えば、今からプロ野球選手になりたいとは思わないですよね。
それは、完全に不可能だと分かっているから。
でも「やりたい」と感じたり、
何度も気になって視線が向いてしまうことは、
心のどこかで「自分もやれる」と分かっている証拠です。
だから余計、自分より前を進んでいる人の存在がまぶしくて苦しい。
だからあえて
「違う世界の人」と線を引いてしまうのです。
この心理の厄介なところは、
「比較」そのものが悪いわけではない
という点です。
比較はときに強烈な原動力になります。
「あの人が頑張っているから、私もやろう」
というポジティブな比較もある。
問題は、その比較を
「自己否定」に使ってしまうこと。
自分の価値を下げる材料として比較するから苦しくなるのです。
つまり、「比較する自分」を
責める必要はありません。
比較してしまうのは自然なこと。
ただし、その比較をどう扱うかで未来が変わるのです。
たとえば、
「あの人は毎日発信している。すごいな」
ではなく、
「じゃあ私は週3回やってみよう」と、
自分なりの目標に変換する。
あるいは「人前で話すのが苦手」ではなく、
「人前で話す練習をしている仲間がいる。私も小さな一歩を真似してみよう」
と捉える。
比較を〝刺激〟に変えられれば、
それは成長のための燃料になります。
「比較=劣等感=苦しいもの」
という回路で止まってしまうから、
「見ない」「関わらない」という選択をとる。
実際には、それが一番もったいないんです。
こうして気づけたら、次は「認める」こと。
「私は今、燃えていないんだ」
と素直に認めることです。
ここを飛ばしてしまうと、
いつまでも自分を責めたり、
ごまかしたりして苦しくなります。
燃えていないときは燃えていない。
それでいいのです。
その上で「じゃあ、どうやって火を点け直すか」を考えればいいのです。
火を点け直す方法は、
決して特別なものではありません。
小さな行動でいいのです。
それだけでも「やった」という証拠になります。
その積み重ねが自己信頼を育て、
大きな挑戦へとつながります。
そして、もうひとつ大事なのは
「燃えている人に近づくこと」
です。
人は環境からも強く感化されます。
さっきもお伝えした通り、
燃えている人を見ると、
劣等感や嫉妬が湧くのは当然のこと。
でも、それを避けずに近づいていくこと。
火のそばにいれば、自分にも火は移ります。
羨ましいと感じた人にこそ、
「真似する」という形で近づく。
すると少しずつ、自分の熱も高まっていきます。
しずかさんも、最初は怖くて見ないふりをしていましたが、
やがて「やっぱりやりたい」と、
Threadsでアウトプットを始めました。
やってみると、想像していた恐怖よりもはるかに小さいです。
行動はいつも、頭の中で膨らませた恐怖よりも軽い。
大切なのは、最大火力を目指さないこと。
小さな火を絶やさず、一定の熱で続けていくこと。
それがぬるま湯から抜け出す方法です。
さぁ、ここであなたに問いかけたいと思います。
「いま、あなたが気になっていることは何ですか?」
「本当はやりたいのに、目をそらしていることはありませんか?」
それが答えです。
気になっているのなら、もうやれるのです。
気づき、認め、行動をしていく。
この流れを繰り返すことで、
いつの間にかあなたの内側には
消えない火が育っていますよ!
しずかさんのお話を書いている記事もよければ↓